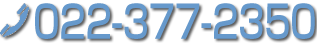【2025年11月26日 8:00 PM更新】
こんにちは
仙台市泉区・富谷市からも近いただ歯科クリニックです。
初めての方はこのブログの簡単な注意事項こちらの記事に目を通してください。
こんなお悩みないですか?
「うちの子、よく噛まずに飲み込んじゃう…」
「食事に時間がかかる」「そもそも食べるのが苦手そう」

そんな悩みを抱えるお母さんは、とても多いです。
そして多くの方が、どこかで
「ちゃんと噛んで!」と声をかければ直るのでは?
と感じてしまいます。
ですが、私は歯科医師として多くの子どもを診る中で、
“噛めない”のは性格やしつけの問題ではなく、
身体の感覚や成長プロセスに理由がある
ということを、何度も目にしてきました。
この記事では、
-
なぜ「噛めない子」が増えているのか
-
感覚統合(触覚・固有感覚・前庭感覚)と噛む力の関係
-
叱らずにできる、家庭でのケア
-
食べ方・姿勢・行動の背景にある“理由”
これらを、専門家として できるだけ分かりやすく、優しい言葉で お伝えしていきます。
あなたの育児を否定する内容ではありません。
むしろ「だからうちの子はこの食べ方なのか」と知ってもらうことで、必要以上の声掛けがいらなくなると思います。
1. 「噛めない子」が増えている本当の理由
まず大前提として、
噛む力は、生まれつき備わっているものではありません。
赤ちゃんの頃は「吸う」力が中心で、
成長とともに「押す」「つぶす」「噛む」へと発達していきます。
また、こういった機能の発達は。発育とは違うので年齢が上がると勝手に噛めるようになるものではありません。
■理由①食べやすい食事が多い
離乳食から幼児食まで、昔より食事が食べやすくなりました。うまく噛めないから食べやすくしてしまうと、食べてはくれるけど、口の機能はそのままです。
-
歯ぐきを使って“つぶす”経験
-
奥歯で“押しつぶす”感覚
-
舌で食べ物を“まとめる”動き
こうした経験が不足すると、噛む動作が育ちにくくなります。
■理由② 生活スタイルが「口を使わない」方向へ
長時間のスマホ・タブレット、テレビ視聴や会話の現象は、口や表情筋が動く機会を減らします。
また、屋外遊びの減少は、体幹や姿勢、呼吸の発達にも影響します。
姿勢が崩れると口元の筋肉も弱くなるため、噛む力にも直結します。
■理由③ 感覚統合の発達のアンバランス
ここが“叱っても治らない”最大の理由です。
噛む動作は単純な筋力運動ではなく、
「感覚」と「運動」が連動して働く複合的なスキルです。
つまり、
口の中に入った食べ物の場所を感じる(触覚)
どのくらいの力で噛めばいいか(固有感覚)
姿勢を安定させる(前庭感覚)
これらがバランスよく働くことで、はじめて「噛める」ようになります。
子どもが噛めないとき、実はこの“感覚”のどこかが育ち途中の場合が多いのです。
2. 噛めない子に多い「感覚のクセ」
多くのお母さんが見逃してしまいがちなポイントを、
やさしく解説します。
■触覚の問題:口の中の“位置”が分かりにくい
こんな様子はありませんか?
-
食べ物を口の端に溜めてしまう
-
口に入れた後、飲み込むまでに動きが少ない
-
食感のある食べ物を嫌がる
-
よだれが出やすい
-
麺類を噛まずに飲み込む
これらは、
口の中の触覚が十分に育っていないサインかもしれません。
食べ物の位置が分かりにくいと、舌で食べ物を上手にまとめられず、結果として「噛む前に飲む」という行動が起こります。叱っても改善しないのは、「感覚が追いついていない」だけだからです。
■固有感覚の問題:噛む力の調整が苦手
固有感覚とは、
「どのくらいの力を入れればいいか」を感じるセンサーです。
ここが未熟だと、
-
すぐに噛みすぎてしまう
-
逆に、いつまでも噛まずに口の中に残す
-
食べ物の“硬さ”に不安を感じる
-
口を閉じて噛み続けることが難しい
といった行動が見られます。
子ども自身は決して怠けているわけではなく、「どのくらい力を入れればいいか分からない」そんな状態なのです。
■前庭感覚・姿勢:姿勢が崩れると、噛むことはもっと難しい
噛む動作には、
実は“体幹の安定”が欠かせません。
以下のような特徴がある子は要注意です。
-
食事中にすぐ姿勢が崩れる
-
体が斜めになる/背中が丸い
-
足がブラブラしている
-
肘をついて食べる
-
椅子に座るのが苦手
姿勢が安定しないと、あごの動きにも余計な力が入ってしまい、噛む力をうまくコントロールできません。
3. 叱らなくて大丈夫。“感覚が育つと噛めるようになる”
ここまで読んでいただいた方なら、もうお気づきかと思います。
噛めないのは、子どもの努力不足ではありません。
感覚と体の発達が“今、ちょうど育ち途中”なだけです。
だからこそ、「ちゃんと噛んで!」という声かけだけで改善することは難しいのです。
むしろ、声かけがプレッシャーになると、子どもは“早く飲み込む”ことで逃げようとします。
必要なのは「叱らない」「責めない」「環境を整える」この3つだけです。
4. 今日からできる“家庭でのケア”
ここでは、お母さんが毎日の生活の中でできる
優しいアプローチをご紹介します。
■① 足を床につけて食べる習慣を
姿勢の安定は、噛む力の土台です。
-
足置きをつける
-
椅子の高さを調整する
-
テーブルの高さをあごより少し上に
これだけでも噛む力は大きく変わります。
■② 食事前の“口のストレッチ”
食べる前に30秒だけ、口周りを温めたり軽くマッサージすると、
触覚が目覚めやすくなります。
例:
-
ほっぺを円を描くようにクルクル
-
唇を軽くつまんでパッと離す
-
舌を左右に「ペロッ」と動かす
- 頬を膨らませる
たったこれだけでも、噛む力はふわっと出やすくなります。
■③ 親は「実況中継」でOK
叱る代わりにおすすめなのが、“実況中継”スタイル の声かけ。
-
「今、たくあんパリパリ音がしているね」
-
「キノコからおつゆがジュワって出たでしょ」
-
「ゆっくり噛めてるよ」
こうした言葉は、触覚や固有感覚の“気づき”を助け、子どもが自分の動きを理解しやすくします。
■④ 外遊びは“噛む力”への最高の投資
実は、噛む機能を伸ばす一番のトレーニングは、
食事中ではなく 外遊び です。
-
ブランコ(前庭感覚)
-
鉄棒/うんてい(固有感覚)
-
公園の凸凹道を走る(姿勢制御)
これらは「噛む―飲み込む」の基礎づくりに直結しています。
遊びは、食べ方を変えるための最高のリハビリです。
5. “なんで噛めないの?” その理由を知るだけで、子育ては楽になる
この記事で伝えたかったのは、「噛めない」には必ず理由があるということ。
そしてその理由の多くは、お母さんの育て方とは無関係 だということです。
むしろ、子どもは今、一生懸命に“育っている途中” なのです。
だから、
-
怒らなくていい
-
無理に噛ませなくていい
-
周りと比べなくていい
ただ、子どもの体と感覚のペースに合わせて、少しだけ環境と声かけを変えてあげれば、子ども達は自然と「噛める体」に育っていきます。
あなたの子育ては、もう十分がんばっています。そして、お子さんはその中で確実に成長しています。
噛めないのは問題ではなく、まだ伸びしろが残っている というだけのことなのです。
口の発達は全身の発達とつながっています。
それを知ることで子供を引っ張る子育てから背中を押して成長を助ける子育てに変わります。
まずはご相談ください。
こういった定型児の「食べる」機能の問題がある子供の一部は2018年から「口腔機能発達不全症」という病名で保険診療での治療の対象になることがあります。ただし、歯並び・かみ合わせの問題がある場合、矯正治療と同時に行うのは混合診療になるので、当院では矯正治療を行う場合は、矯正治療の中で指導をしています。また発達障害等の症状がある子供にはより専門的で細やかな介入や指導が必要になることがあります。
矯正の無料相談を行っています。(要予約)
無料相談では費用や期間だけでなく、患者さんの現在の今の状態、なんでこうなってしまったのか?そういったことを話します。矯正の無料相談は、診療日のどの時間でも対応していますが、必ず予約して来院してください。
メール予約:こちらをクリックしてください
お口の中を拝見していない状態でのメールや電話での問い合わせにはお答えしかねます。
無断でのキャンセル・何回も予約を変更するなどがあった場合お断りすることがあります。
注意事項
*このページはただ歯科クリニックのブログです。あくまでも当院のの考えに基づいて書かれているもので、他院では診断・治療法・介入のタイミング等は違うことがありますのでご注意ください。
*このページの内容を無断で使用することは固くお断りいたします。
*医療法の改正に基づき術前術後の写真は掲載してません。無料相談時に類似症例を用いて説明をさせていただきます。
前へ:食べると口の中に物を詰め込みすぎてしまう
次へ:偏食が治らないのはワガママじゃない。(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【2】)
カテゴリ【感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する】の関連記事
(2026年2月11日更新)
よく転ぶ子は“固有覚”が弱い? 歯科で見える意外なサイン─(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【11】)
(2026年2月4日更新)
寝つきが悪い子ども─(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【10】)
(2026年1月28日更新)
発語が遅れている幼児に隠れた「口腔機能」のサインとは —(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【9】)
(2026年1月21日更新)
猫背の子に“共通して見られる”口腔機能のサイン──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【8】)
(2026年1月14日更新)
子どものいびきは“成長のサイン”かもしれません──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【7】)
Blogメニュー
- 小児歯科お悩み相談室【13】乳歯の生え変わりが早い・遅いってどう判断?安心できる目安まとめ
- 小児歯科お悩み相談室【12】1〜2歳で歯が少ないときの“まず見るポイント”
- よく転ぶ子は“固有覚”が弱い? 歯科で見える意外なサイン─(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【11】)
- 小児歯科お悩み相談室【11】感覚が敏感・鈍い子と噛む力の関係をゆるく解説
- 寝つきが悪い子ども─(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【10】)
- 発語が遅れている幼児に隠れた「口腔機能」のサインとは —(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【9】)
- 小児歯科お悩み相談室【9】ミルクを嫌がるのはなぜ? 感覚統合から見る赤ちゃんの“飲みやすい”姿勢
- 猫背の子に“共通して見られる”口腔機能のサイン──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【8】)
- 小児歯科お悩み相談室【8】「飲む・食べるが苦手かも?」 小さなサインに気づく哺乳と離乳のヒント
- 子どものいびきは“成長のサイン”かもしれません──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【7】)
- 小児歯科お悩み相談室 (12)
- 感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する (11)
- 口腔機能発達不全症 (45)
- インビザライン目立たないマウスピース矯正 (2)
- ただ歯科クリニックからのお知らせ (21)
- 歯についての話 (4)
- 不正咬合・悪い歯並びの種類について (21)
- 大人の前歯4本の部分矯正・目立たないマウスピース矯正の話 (13)
- 中学生・高校生・成人のSH療法 (10)
- 小児矯正・子供の歯並び・小学校低学年の矯正治療 (64)
- 矯正治療の費用について (6)
- 矯正治療の抜歯・歯を抜かない矯正について (2)
- きれいな歯並びになる子育てのヒント (89)
- お子さんが虫歯にならないための話(虫歯予防) (18)
- 歯ブラシ・歯磨き粉のお話 (9)
▶Blogトップへ戻る