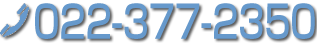【2025年10月15日 9:21 AM更新】
こんにちは
仙台市泉区・富谷市からも近いただ歯科クリニックです。
初めての方はこのブログの簡単な注意事項こちらの記事に目を通してください。
子どもの“口の機能”って見ていますか?
「うまくかまずに飲み込んでいる」「発音がもごもごしている」――こうした“ちょっと気になる様子”を、なんとなく“癖”と思っていませんか?
でも実は、口腔機能発達不全症(こうくうきのうはったつふぜんしょう) のサインであることがあります。
この病名は比較的新しく、2018年(平成30年)から日本でも公的保険で扱われるようになりました。大体子供の15%前後にいると言われています。
このブログでは、
-
どんな子どもが「適用」になり得るのか
-
口腔機能発達不全症が「改善すべき点」
-
どのようなアプローチ(診断・治療・トレーニング)があるか
ということを解説していきます。
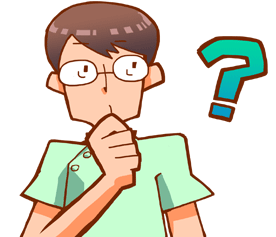
1.「どんな子」が対象になる?── 適用となる子・兆候
対象年齢と前提条件
-
基本的には 18歳未満 の子どもが公的保険の対象です。
-
ただし、器質的・疾患的原因がある子は対象外で、“健常児”の中で、口の機能の発達が遅れている子供が 対象になります。。
-
診断基準としては、厚生労働省/日本歯科医学会が定める チェックリスト形式(C‑1〜C‑12 など) のうち、一定数以上の項目が該当することが必要です。
子どもに見られがちな“気になるサイン”(早めにチェックしたいポイント)
以下のような特徴が複数あれば、口腔機能発達不全症を疑ってよいでしょう:
| サイン | 内容・例 |
|---|---|
| よくかまずに飲み込む/丸飲み傾向 |
食べるのは早いが、噛んでいない。 食べこぼしが多い、むせることがある |
| いつも噛む側が決まっている(偏咀嚼) | いつも同じ側で噛んでいる、嚙み合わせや歯列、顔がゆがんでいる |
| 発音・滑舌の問題 | 特に「サ行」「ラ行」がはっきりしない、発語の遅れなど |
| 食事に時間がかかる | 柔らかいものばかりを好んで食べる。ちょっと厚い肉や硬いものや葉物野菜がうまく噛み切れなくて出してしまう。 |
| 口唇閉鎖不全(ポカン口)/口が開いている | 安静時に口がぽかんと開いている |
| 指しゃぶり/口腔習癖 | 指しゃぶりがやめられない、舌で歯を押す癖など |
| 食べるのが遅い | 給食で1週間のうち半分以上間に合わない日がある |
たとえば、「口をいつも開けている」「食べるのに時間がかかる」「言葉がはっきりしない」など、保護者が普段目にする小さな違和感が実はサインになっていることが多いです。また家庭では気にしていなかったことが、学校給食という「同じもの、同じ量で、同じ時間内に食べる」となったときに時間内に食べ終わらない、いつも給食を残してしまう、食べれないものが多い、などの問題が出てくることがあります。これらのサインが 複数重なる 場合には、かかりつけの歯科医院や小児歯科へ一度相談してみることが望ましいです。

2.何を改善していくのか?── “機能発達”の遅れを取り戻す
口腔機能発達不全症では、主に以下の3つの機能領域の改善・育成が目標になります。
| 領域 | 具体的に改善すべき点 | なぜ改善するのか(リスク回避の視点) |
|---|---|---|
| 食べる機能(咀嚼・嚥下) | よくかむ力、口腔内での食べ物操作、飲み込みの協調性 | 咀嚼・嚥下の機能が未熟だと、丸飲み・むせのリスク、消化負荷、偏食、栄養摂取のアンバランスにつながることがあります。 |
| 話す機能(発音・構音) | 舌・口唇・顎の運動性、滑舌、正しい音の出し方 | 発音が不明瞭なままだと、コミュニケーションの自信低下や学習機会への影響が出ることがあります。ORTC+2GC+2 |
たとえば、「ひと口で30回噛みましょう」とよく言われます。何もしないでカチカチ30回噛んだあとに、鼻をつまんで30回噛んで見てください。噛みにくくなるはずです。口呼吸の子供の食事はそんな感じです。正しい鼻呼吸が獲得されていないことで噛めないために、丸呑みをしてしまいます。
噛まないことで、正しい顎の発育が遅れ、歯並びやかみ合わせにも影響が出たりしてきます。

3.どうアプローチする?診断・治療・トレーニングの流れと実際
口腔機能発達不全症への対処は、“見つける → 評価 → トレーニング → 継続的なフォロー” というステップで進められます。
診断・評価のステップ
-
問診・ヒアリング
母親・父親から「食べ方・飲み込み・発音など」について丁寧に聞き取ります。 -
診査
現状の口腔機能の確認をします。また、厚生労働省/日本歯科医学会の C-1~C-12 チェックリスト を用いて、該当数を確認します。
G -
診断
チェックリスト該当数や機能検査結果をもとに、「口腔機能発達不全症」と診断します。 -
治療計画の立案
子どもの年齢・発達度合い・機能的弱点を踏まえ、食事の指導など具体的なトレーニングの計画を立案します。
ただ歯科クリニックでのトレーニング・アプローチ
口腔機能の発達には様々なアプローチがあります。当院では口腔機能の定型発達をしている子供たちができている食べること、食事の指導を中心に「食べる機能」の発達の遅れを取り戻します。また口の発達の遅れだけが局所的に起こっていることは少なく、全身発達の遅れも同時に起こっていることが多いことから感覚統合の考えを応用して、食べる機能、話す機能にアプローチをしていきます。
例えば噛む力がない子供に対して、噛めないから硬いものを噛んでもらうという指導ではなく、日常背生活の中で歯を食いしばるような力が入る運動をしてもらう。例えば口をポカーンと開けながらジャングルジムを登ったり、ブランコに立って乗るのは難しいように遊びの中でそういったものを取り入れたりしていきます。
*指導方法や問題点へのアプローチは各歯科医院で変わります。
フォローアップと見直し
-
指導・トレーニングを始めてから 12か月 で再評価を行います。
-
一定期間の間隔を開けながら再評価をして、必要なら再指導も行います。
4.まずはよく子供を見ることから始めましょう
まずは「あれ?」とお母さんが感じることが大事です。
-
残さないで食べたかどうかではなく、どう食べているか子供の食事を観察する(噛まないで早く食べてもいけないし、ずっともぐもぐ噛んでいるのも問題。)
-
話しにくい言葉がないか注意(例えばサクラを「タクラ」と間違って覚えて言っているのか、本人はサクラと言っているのに、「タクラ」と聞こえているのか)
-
好き嫌いが味ではなく、同じような食感のもので食べないようになっていないか(味の好き嫌いは様子を見ていいのですが、同じような食感のもの硬さのものを食べなかったり、柔らかいものばかり食べたりしていないか)
- 飴や氷を舐めないでぼりぼり噛む。飴や外食のジュースに入っているような小さめの氷を舐めないでぼりぼり噛んでしまう。
歯並びやかみ合わせに問題がある場合は保険外の矯正治療が必要な場合があります。
例えば口呼吸と一般的に言われるものの中には、歯並びやかみ合わせが悪くて口が閉じれない「歯性の口呼吸」と習慣的に口が閉じれない「習慣性の口呼吸」があります。口腔機能発達不全症の適用は習慣性の口呼吸で、歯性の口呼吸は保険外の矯正治療の適用になります。その場合口腔機能発達不全症との同時の進行は混合診療になるので、矯正治療の中で当院では機能面のアプローチや指導をしていくようにしています。
口の機能の発達が悪くて、歯並びやかみ合わせに影響が出ることがありますが、多くの場合は歯並びやかみ合わせを改善しないで機能面だけ改善しようとしても難しい場合が多いので、そういったケースには矯正治療のお話をさせていただく場合があります。
また必要に応じて多職種との連携が必要になることがあります。
例えば話す機能の場合、言語聴覚士の方との連携(特に就学時以降で学校に不定期に言語聴覚士が来て指導を受けている場合等)。
5.まとめ:早めの気づき・継続サポートが鍵
口腔機能発達不全症は、“軽い癖”と思えるサインから始まることが多く、親御さんが小さな変化に気づくことが第一歩です。
子ども自身は自覚がないことも多いため、お母さんの「ちょっと変だな?」という感覚を大切にして、早めに専門医に相談してみてください。
改善には時間や努力が必要ですが、早期に適切なアプローチを始めれば、将来リスクを抑えながら子どもの口腔機能の発達をさせることができます。
注意事項
*このページはただ歯科クリニックのブログです。あくまでも当院のの考えに基づいて書かれているもので、他院では診断・治療法・介入のタイミング等は違うことがありますのでご注意ください。
*このページの内容を無断で使用することは固くお断りいたします。
*医療法の改正に基づき術前術後の写真は掲載してません。無料相談時に類似症例を用いて説明をさせていただきます。
前へ:【口腔機能発達不全症4】あなたの子供は大丈夫?口腔機能発達不全症チェックリスト
次へ:好き嫌いが多いい偏食で悩んでいませんか?
カテゴリ【口腔機能発達不全症】の関連記事
(2026年1月14日更新)
子どものいびきは“成長のサイン”かもしれません──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【7】)
(2026年1月7日更新)
食べるのが遅い子の共通点5つ──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【6】)
(2025年12月24日更新)
宿題に集中できない理由が“口腔機能”と関連? (感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【5】)
(2025年12月17日更新)
ハイハイが短かった子は噛む力が弱い?(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【4】)
(2025年12月10日更新)
椅子にじっと座れない子どもの“口の機能”とのお話 (感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【3】)
Blogメニュー
- 小児歯科お悩み相談室【8】「飲む・食べるが苦手かも?」 小さなサインに気づく哺乳と離乳のヒント
- 子どものいびきは“成長のサイン”かもしれません──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【7】)
- 小児歯科お悩み相談室【7】 “乳歯だから歯並びは大丈夫”ではない理由をわかりやすく解説
- 食べるのが遅い子の共通点5つ──(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【6】)
- 小児歯科お悩み相談室【6】寝相と歯並びの関係って?ぐっすり眠れる環境づくりのコツ
- 小児歯科お悩み相談室【5】気づきにくい“歯並びのサイン”をやさしくまとめました
- 宿題に集中できない理由が“口腔機能”と関連? (感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【5】)
- 小児歯科お悩み相談室【4】最近“噛めない子”が多いのはなぜ?食べ方とお顔の関係
- ハイハイが短かった子は噛む力が弱い?(感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する【4】)
- 小児歯科のお悩み相談室【3】乳歯のうちにできる“将来の矯正費を守るコツ”
- 小児歯科お悩み相談室 (8)
- 感覚統合 × 口腔機能からやさしく理解する (7)
- 口腔機能発達不全症 (41)
- インビザライン目立たないマウスピース矯正 (2)
- ただ歯科クリニックからのお知らせ (21)
- 歯についての話 (4)
- 不正咬合・悪い歯並びの種類について (21)
- 大人の前歯4本の部分矯正・目立たないマウスピース矯正の話 (13)
- 中学生・高校生・成人のSH療法 (10)
- 小児矯正・子供の歯並び・小学校低学年の矯正治療 (64)
- 矯正治療の費用について (6)
- 矯正治療の抜歯・歯を抜かない矯正について (2)
- きれいな歯並びになる子育てのヒント (89)
- お子さんが虫歯にならないための話(虫歯予防) (18)
- 歯ブラシ・歯磨き粉のお話 (9)
▶Blogトップへ戻る